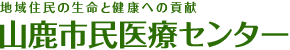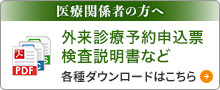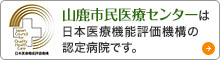山鹿市民医療センターからのお知らせ
2025年3月7日
【質問項目】
1)医科歯科連携に対してどのようなイメージをお持ちですか
2)連携したことで感じたメリットはありますか
3)連携するにあたり市民医療センター(連携先)に望むことがありますか
4)その他
歯科)アンケート回答日 令和7年3月3日(n=14)
❶
アンケートに対する率直な忖度なしの回答をします。
1) 大命題として医科、歯科ともそれぞれ主治医として患者さんの「幸福」のために惜しみなく連携するのは重々理解しているが、日々の診療に追われて「連携」への時間を割くことが「億劫宇」になりがちです。
歯科から医科へで言えば、日々「局所麻酔」を行い外科処置を行うことがかなりの割合を占めているにも係わらず患者の全身状態や服薬を「一々」対診、連携するタイムラグが無駄?と感じて、歯科医師自がが「理論武装」をすることで患者を服薬履歴や、検査結果を判断しているのが現状です。(抗血小板薬。抗凝固薬、骨粗鬆症への投薬とMRONJの発生の可能性、降圧薬の種類や複数の服用の意味、糖尿病の状態がどのくらいなのかをHbA1cや血糖値を患者から聴取して服薬中の薬の種類から類推したり、血液疾患への検査値からの類推など)もっと敷居が低くなれば「聞きやすい」環境が醸成されるかも?とも考えますが、どうしても「主治医への忖度 手を煩わせるのではないか」と考えて、深刻な状況を除いて連携しにくいイメージです。
医科から歯科へで言えば、医科の先生から例えば「周術期の管理」に対して文書を送っていただければ、こちらは一生懸命対応していますが、それ以上に連携することがない(文書を送るだけで終わりとなりがち)感じがします。
2) 一例を挙げるとMRONJを発症したPtに対して、休薬を含めて連携して治癒に向かった経験はありますが、そのくらいですかね。
3) 市民医療センターには「緩和ケア病棟」があり、また当然ながら「一般入院病棟」もあります。誤嚥性肺炎の抑制効果のエビデンスは周知されていると思いますが、もっと「歯科医師会の会員」を使っていただきたい。どうしても「連携のシステム構築」の整備が整っていないのが最大の課題だと考えられますので、医科歯科連携のための協議が必要ではないかと思います。(歯科からのアプローチも全然不足していると思いますが)
また整形外科での手術前の歯科に対する対診(熊本機能病院ではほぼ行っておられ、PJIへの歯周病からのリスクなどについて周術期前の文書交付がある)などのアクションも出来れば行っていただきたいと思います。
❷
1) 連携室が設置されている医科はうまくいっていると思われる。
連携室の無い診療所などでも、連携担当者がいれば問題ないが日頃の付き合いや面識があればいいと思う。
2) 患者さんの全身的な状態や服薬など、多くの情報が得られる。
3) 口腔内にもっと目を向けてもらいたい、とくに担当ナースが口腔内のお困りごと、嚥下や食事に関しての問題点に気づいて主治医に報告して歯科にでつないでほしい。
4) その他
❸
1) 現在の超高齢社会において、全身疾患や服用薬剤を複数、有する高齢者が多く存在するため歯科治療を施す上で医科歯科連携は欠かせないと感じております。
また、近年では全身と口腔の健康が密接に関わっているという報告もありますので今後益々需要は高まると考えております。
2)連携することで私自身も学ぶことが多くありますし、歯科治療を行う上でリスクを軽減できていると感じております。
3) 私自身が歯科医師会に入会して間もない為、わからないのですが今まで行なっていましたら申し訳ありません。医科の知識(特に歯科に関係する分野)を学ぶ機会があればと思います。
4)特にありません
❹
1) 口腔内の炎症(歯周病など)は全身疾患と深い関連がある。
また、全身疾患の初期症状が口腔内所見として現れることもある。このため、医科歯科連携により情報を共有できれば、患者さんに対してより的確な治療を提供することが可能になる、と考えます。
2)以前に比べると、医科からの依頼内容が少し具体的になったように感じます。
3)4)今のところ、特にありません
❺
1) 医師、歯科医師とも何のための連携か理解していない先生が多い
2) ほとんどない
3) 医師、歯科医師それぞれの立場からの勉強会
❻
1) 近年は歯周病をはじめ、歯科疾患が全身に及ぼす影響が明らかになってきたことで、歯科領域だけの背景を問診上から紐解いても患者さんが辿ってきた疾患的道筋、全体像が読めないことが多々あります。各種既往疾患のコントロール状況や内服薬の種類、周術期管理を行う上で全身疾患の把握は包括的な歯科治療を行う上で欠かせない情報源です。医科歯科連携は処置を安全に遂行する上で今後も必要な体制であると考えます。
2) 歯科領域のみでは分からない、採血結果や内服歴、栄養管理法についてなどは特に有益な情報となります。 また、急性炎症時の点滴依頼や歯科領域では処方不可な投薬依頼も快く引き受けてくださいますし、歯科領域のみの診断では不安が残る場合も共診という形で鑑別診断を除外できたりなど心強いです。
一方で、かかりつけ医や入院病棟先でも歯科領域特有の悩み(顎骨壊死の管理や義歯修理、口腔ケア・摂食嚥下など)で悩んでいらっしゃる医科の現場にも遭遇することがあり、私達歯科領域の知識が医科の現場で役立った経験もありました。
3) 医科と歯科で互いの現場で「何が不透明なのか」を明らかにした上で正確な情報のやり取りの橋渡しを切れ目なく行って頂ければ幸いです。やり取りが増えていくことで、医科も歯科も互いの知識が少しずつアップデートされ、臨床に役立つ経験値や対応バリエーションが豊富になっていければと思います。
4) 医科歯科の連携で困ったことやトラブルになるような事例があれば、そういったマイナス面も情報共有し、周知して頂きたいです。
今後そうならないようにはどうすれば良いかを各現場でディスカッションし、業界特有の諸事情(職場文化や伝統など)や治療決定権の優位性についてなどに配慮した行動がお互いに取れるのではないかと思います
❼
1) 患者さんの情報を共有することで様々な治療効果が高まり、患者さんに対する貢献度が上がる。
2) 投薬の無駄を省き、安全な歯科治療を提供できた。
3) 口腔の状態によっては歯科治療に時間を有するケースもありますので、医科の治療開始のある程度の期日をお教えいただけると治療計画が立てやすいです。
4) 先生方や看護師さん、スタッフの方々との交流を持てるとより連携が進むのではないかと思います。
❽
1) 医科歯科連携について、未だ医科の先生とのお互いの認識不足をやや感じます。
2) 患者さんの質が向上するや免疫力の向上につながることが、理解されていないように感じます。入院日数の短縮に繋がることなど。
3) 医師や病院同士の交流が少なく医科歯科連携が取りにくいように感じます、もう少し患者さんの歯や口腔管理にも関心を持って欲しいです。
❾
1) 連携の仕方がわからない。
2) あまりありません。
3) ありません。
4) なし。
❿
1)、2) 医科との情報伝達の迅速化と正確さに寄与できるイメージがあり、メリットとしても同様に感じてる。
3)、4) 特になし。
⓫
1) 超高齢社会に突入して社会構造の変化だけでなく疾病構造も大きく変化してきている。
今後さらに医科歯科連携は必須のものだと考えるが現状はまだまだ連携の意識が低いのではないかと思う。
2) 患者さんの全身状態が把握できた。全身麻酔における周術期の口腔ケアがだいぶ定着してきて患者さんの口腔内に対する意識が高くなってきたような気がする。
ただ、周術期のオペ前は、来院されるが退院後の継続治療に結び付いていない。
3) 山鹿市の中核病院として連携事業の中心になっていただきたい。
4) 以前の経験であるが、訪問に行ったときに内部の連携がうまくできていなったことがあった。
⓬
1) 基礎疾患を持つ方が多いので、情報共有することで安全で効果的な医療を提供できる。継続した医科歯科連携は難しい。
2) 治療中断していた方が手術をすることになり、術前の口腔ケア依頼で来院され、その後も継続して通院されている。健康状態について患者に聞くと曖昧な事があり、かかりつけ医に問い合わせた回答を得ると安心して治療できる。
3) 手術を行う前に口腔ケアや治療をすることが多くなってきている。
また保険で算定可能な手術も多いので、是非、術前の口腔ケアや歯科治療の依頼をお願いしたい。
※市民医療センターの年間の手術数からすると、依頼が少ないと思います・・・。
⓭
1) 歯科から医科に連携をお願いするにはハードルが高く感じる。
2) 患者様が医科歯科が連携していることで自分の体の状態を理解してもらえるので安心して歯科治療を受けられているように思う。
3) 外来、入院中の患者様の口腔内の事に関して些細なことでも構わないので歯科に照会してほしい。
4) 特になし。
⓮
1) 周術期等の連携に関して、とても重要だと感じている。
2) 周術期で依頼された方の、術前術後の健康状態の安定につながればありがたいと感じています。
3) 特にありません。
4) 今後とも医科歯科連携の強化をお願いできればと考えています。
医科)アンケート回答日 令和7年3月3日(n=3)
1) 医科歯科連携に対してどのようなイメージをお持ちですか。
口腔内細菌叢が特にがんの発生、予後、治療(特に手術)の合併症 に影響する、という報告は 多数あるので連携は望ましいと思います。
最近重要性が増しているので良いと思います。
良いと思います。
2) 連携したことで感じたメリットはありますか。
周術期のう歯による感染性合併症や挿管時の歯牙損傷のリスクは下がると思います。
術前の歯のチェックをしてもらえること。
術後の感染性合併症の軽減ができる。
3) 連携するに当たって歯科に望むことはありますか。
早期受診加療。
口腔ケア、う歯の治療等。
今後もよろしくお願いします。